連載「おきたまに根をはって」
第7回 悪戦苦闘する農業――いま、農村で何が起きているか(下)
B章 地域農業のもう一つの途(みち)
共同代表 菅野 芳秀
1,地域農業のもう一つの途
いきなり、まったく違う話を接ぎ木するようだけど、ここからは違う角度で見てみたい。我々は1989年の国際民衆行事であるピープルズ・プラン21(pp21)を開催し、以来、目指すべき農業・農村の有り様を7つの要点に整理し、それを行動規範として現実に挑んで来た・・と書けば勇ましいが・・。共有できる観点だと思う。まず、それを取り組んで来た地域実践と共に、簡単に紹介したいと思う。
①生態系を乱さない農法。
農薬の大型ヘリコプターによる空中散布の反対運動。そしてその地域的展開。それを皮切りに、置賜(3市5町・・20数万人)から空中散布を無くした。そしてゴルフ場反対運動。ゴルフ場はすごく農薬を散布する。それが流れて水田に至る。土壌汚染を招く、水質、飲料水の汚染も。それへの反対運動を行い、その計画を断念に追い込む。河川の飲料水取り入れ口の上流への大型焼却所建設計画を中止に追い込む。ほぼ1ヶ月で住民の9割の反対署名を集め、中止に追い込む。減農薬米運動を地域的に展開する。(「七転八倒百姓記」現代書館参照)
②「循環」を地域的に実践する。
循環を地域的に考えるレインボープランなどの実践。それがやがて、自給圏を担っている運動になる。これも「七転八倒百姓記」現代書館を参照
レインボープランは町の生ゴミを活用して、消費者、生産者の区別なく、土に関わり、農に参加する地域づくりだ。堆肥がないから土作りができない。土作りができなければ、農薬散布やむなしという農協の論理とずいぶんやり合いながら、農協を批判するだけではなく、ともに課題を解決する方向で連携し、建設的な減農薬運動を進めてきた。
③多様性の共生社会としての地域社会の実現。
多様性の共生社会として、共に生きていける社会をどう作り出していけばいいのか。様々な方々と連携しながら同じ地域の生活者として、イコールの立場で協力し合いながら、ともに生きれる地域社会を作り出していく取り組み。
④地域の自立と自給。
新しいローカリゼーション。都会の植民地にならない自律的な地域をどう作るか。そこから「置賜自給圏」につながって行った。
⑤参加民主主義。
地域の命運を国家に預けない。操縦桿を地域住民が握る。住民自治
廃県置藩。藩とは自給圏。置賜自給圏を建設する取り組みにつなぎ、今日に至る。
⑥地球的視点。
⑦ともに生きるための農業。
農家に限らず、望めば農に関われる「国民皆農」への道づくり。
これも置賜自給圏を建設する取り組みにつながって、今日に至る。
この7つの条件を重ねて向こう側に見える社会こそ、我々が目指すべき地域社会ではないか。そう捉えながら、地域実践を重ねて来た。
2)新しいローカリゼーションへ
今の国の農政にあっては、経済効率一辺倒で、兼業、専業問わず、家族農、小農を淘汰し、規模拡大をすすめること。これは「鉄の法則」として位置づけられている。そんな嵐の中、俺たちは小農と市民の生活者連携を主体に、次代に向けた食といのちの連携を足元から築いて行こうとする。その陣地を地域的に築いていく。その規範が「七つの条件」だった。俺たちは、その道を歩み続けてきたし、これからもこの道を歩み続けたいと思う。
今は時代の転換期。理想を決意に変え、創り出す時代。単に克服すべき時代のものさしを批判するだけでなしに、それを乗り越える新しい基準を提案すべき時代だ。
転換期の時代性・世界性・地域性を孕んだ地域政策を持って難局に参加をする。
経済効率一辺倒のグローバリズムの限界はとっくに明らかだ。それとはまったく違う、新しいローカリゼーション。地域自給圏。その具体的建設に向けた農民と市民の連携。
国民(市民)皆農を織り込んだ新しい道。我々もその道を行く。
だが、農業・農村では今まで見てきたように、自民党政治の中、効率性と大規模農業が大きな勢いをもって跋扈している。食の安全性、食の持続性、自然環境を守らんという視点は、後方に引っ込められてしまったかのようだ。具体的に小農、家族農が離農に追い込まれ、いまや「農仕舞い」の言葉すら農村では交わされている。
そのただ中、そうじゃない地域政策、そうじゃない地域作り、そうじゃない人と人との繋がりをどう作っていくのか。繰り返すが、みんなが農業に関わり、みんなが土と関わり、みんなが命の世界と関わる農的世界の実現。地域の操縦桿を国から地域住民に取り戻す。自民党から民衆に取り戻す。国は沈んでも自分たちが生活は破綻しない地域作り、地域の主体性・自立性を地域のローカリゼーションとして作り出していく。その為にも農民と市民の連携が求められている。
3)新しい希望の創造に間に合うか
小農こそ、社会性、地域性をはらむ希望への架け橋。可能性である。ただ、次代の希望に間に合うのだろうか。ボロボロと小農がこぼれていく。
数十町歩、新潟では1000町歩を超える大規模農業が始まっているという。それは小さな農家をつぶしていった結果だ。村には累々たる小農の屍が横たわる。
農の持つ全ての可能性が壊されつつある。先日、百姓交流会の有力メンバーが「菅野、俺百姓を辞めることにしたよ。これ最後のブドウだ」と言って持ってきてくれた。
彼に今回のレジュメを見せた。
「その通りだな」と言う。「次の希望に間に合うと思うか。家族農、小農が絶滅的寸前になっている現状を克服し、次の代にタスキを渡せるか?」「まずねえべな」と彼は言っていた。
ほぼ50年間、農業、農村の中でいろんな運動を続けてきた。戦後、475万自作農家が、村からこぼれていく過程を脇で見ながら、そうではないオルタナティブな運動を提案し実践的にも関わってきた。楽しみも、困難さも含めて経験してきた。今、突き当たっているのは、この先がないことだ。安易に展望は描けない。
こんな現実に囲まれているからこそ、悲観的な話だけでなく、前を向くような話が大事。その視点がなければ橋が出来ない。だけど、肝心の未来への橋をかける百姓が、目の前でこぼれて行く。この現実はとても重い。
「ときが来る」ことは間違いない。でも、佐渡のトキになっている各地の百姓たちとともに、どういう未来作りが可能なのか。それぞれの持ち場の中からいろんな提案をいただきながら、共に未来への架け橋を作っていければと思う。
以上
新聞テオリア第134号・2023年11月10日掲載 この項完。
連載「おきたまに根をはって」
第7回 悪戦苦闘する農業――いま、農村で何が起きているか
Aの章・・ときがくる、ときになる
菅野芳秀(共同代表理事)
好きではないが、書き始めたら悲観的な話、暗い話になる。
それも仕方ない。3割を超える非正規の日本の労働者の現状を悲観的にならずに、明るく話せるかと言えば、ま、出来なくはないかもしれないが、多くの場合は失笑を買うだろう。冷めた笑いを誘うかもしれない。
農業もそれと同じですね。ここでは無理して明るい話題を拾い集めたとしてもあまり意味が無い。だから、力を抜いて、農村の現状をそのまま話したいと思う。
私は、山形県長井市で百姓をして50年になる。経営の中身は水田が5ヘクタール(5町歩)。それと玉子を得るための放し飼い養鶏を1000羽。
鶏の出すフンを田んぼや畑に。田んぼや畑が生み出すくず野菜は鶏の餌に。他に豆腐工場のおから、学校給食の残飯など有機廃棄物を混ぜながら地域の中でうまく活用し、農業と繋ぐ。自分では地域循環農業あるいは地域社会農業と言っている。
中心は40歳の息子。朝早くから夕方まで働いている。
去年、その息子が百姓やめていいかと言い出した。10年ほど前まで集落40戸のうち30軒が農業をやっていた。たった10年で20軒余りやめた。今は10軒にも満たない。更にここ数年でそれも半分以下となるだろう。
40歳と言えば、地域農業の中心的働き手。地域からもいろんな役を要請され、それを断らずに頑張っていた。そんな息子がそういうことを言い出した。
それはなぜか。おいおい話すが、一緒に考えていただければありがたい。
Aの章
1)いま、稲作、畑作の現場では・・ときがくる、ときになる
「ときがくる、ときになる」。つまり工業系の時代から農業系、生命系の時代への大きな転換期がやって来た。待望の時代の転換期だ。だけれど、本来、その中心にいなければならない俺たち百姓は、佐渡のトキのように絶滅危惧種になろうとしているよ。「ときがくる、ときになる」。
そんな実感を言葉にした。我ながらいい造語だと思っている。
我々の村には、山形新幹線で赤湯駅、そこから長井線に入り、約50分。水田がやけに目につく。平地のほとんどが水田かと思うような風景が続く。
その水田がいま、あっちこっちでブルドーザーが動き、大型基盤整備の最中にある。秋田も新潟も岩手も・・東北各地にも同じような光景が見られる。
我が家の田んぼは1区画15~30アールぐらいに整理されている。日本は山国、傾斜地が多い。大きな区画の水田はなかなか作れない。だから、1区画1・5~2反くらいの水田になっている。そこに新しい基盤整備事業。1区画1町歩だ。100メートル×100メートルの大型区画。今、その基盤整備の工事でブルドーザーがフル稼働している。この事業は無料。工事費は農水省が払う。農家の持ち出しは無し。ただ、基盤整備工事中、米は作れないから、そこは黙って了解してくれと。
結果として、小農が生きていけなくなった。つまり1区画1町歩にするが、おまえさんところは出来るのかと問われる。その段階で、機械も買えない、後継者もいないとなると、大型化に抵抗のない農業法人に預けるか・・となってしまう。さながらブルドーザーで小農を潰し乍ら大型化が進んでいるかのようだ。言うまでもなく、大区画の水田には、新しく小農、兼業農家、新規就農者の参加する余地は全く無い。
その農業の担い手は農業法人。中には建設業などが控えている場合もある。その場合、農業従事者は農民ではない。場合によって地域生活者ですらない。
一口に言えば、大農経営には農民がいなくていい。農村すらなくても構わない。それを先取りする様々な現れが既に始まっている。風景が少しずつ変わってきている。
2)生産費を賄えない低米価政策が続く
農民が農業から離れていく・・。そこには様々な原因がある。けっして一つではないだろうが、一番大きな問題は、米価を始めとする農産物の安さ。コメを言えば、ご飯一杯白米で70g。1キロ400円の米を買ったとしても一杯は28円だ。ポッキー4本分。これでもコメが高いと言って穀物を外国に依存しようとする。棄民政治。
今、JA=農協の仮私金で一俵60キロ1万2000円前後。かつて、その価格に近い価格だったの今から50年前の1974年。玄米で一俵1万3615円。当時の新聞価格が月1700円。私は新聞奨学生で新聞配達していたからよく覚えている。今その新聞代が月4900円。1974年から2023年の間で2・9倍になっている。74年当時のコメのJA買取価格をそのまま2・9倍すると、1俵39,483円にならなければならない。だが、現在1万2000円。かつ、4割の減反。減反補助金があるという誤解が結構全国に広がっているが、何もない。
米作りから農家が離れていくのは当然だ。暮らしていけないのだから。こんな国で稲作農業やって苦労するのはごめんだよという事だろう。
日本の米の生産は年間670万トン。一方、輸入される小麦は550万トン、大麦200万トン。それが年々増えている。それが自民党政府の政策だ。農民はどんどんやめていく。離農奨励金が出ているうちにやめようか・・。奨励金・・農業に就くための奨励金ではない。離農奨励金だ。まさに棄農政治だ。
3)農機更新時期が離農時期
稲作は農作業ごとに機械が変わる。田植え機械、トラクター、コンバイン・・。1台あたり安くて400万円。高いのでは数千万円のモノまである。
だけど、米の販売原価から400万は出せるわけがない。農家によっては、親父の年金、母親の年金の助けを借り、何とかかき集めてローンを組み、農機を買おうとする。
国の補助。これが非常に上手くできていて、大規模化を目指せない、あるいは目指さない農家、拡大成長路線を描けない農家には補助金がでない。だから機械が壊れたなら農家をやめざるを得ない。機械が稼働している限り、いつか機械は壊れる。小農だって存続するためには農業機械を更新しなければならない。更新費が出るわけでないから、機械壊れたら、もう農業無理。やめるよとなる。農業機械の更新時期が離農時期になる。
息子の春平が農業やめていいかと言ったのは乾燥機が壊れたからだった。乾燥機は約200万円。どこをつついたってそんな資金は出ない。「友人の工場できてくれないかと言っているから農業やめてそこで働こうか、迷っている。」
結果的にもう少し続けようとなった。家族でお金を捻出して、200万の乾燥機を更新した。次は精米籾摺り機、田植え機。その後はコンバイン、トラクターなどが待っていて
その都度やめるかどうかという深刻な崖っぷちに立たされる。春平だけではない。どこの百姓も同じだ。
次に富夫君の場合。彼は30頭の米沢牛を飼っていて、先日チャンピオン牛を出した。一頭180万円近くで売れる。彼は30頭の和牛と7ヘクタールの水田の組み合わせで、水田の複合経営をやっている。藁を牛に踏ませ、堆肥を作り、それを水田にという循環農業をやっている。白鷹町の誰もが認める農業リーダーだ。
彼も農業機械の更新の為、補助申請に役所に行ったら、規模拡大の成長路線を書けと言われたという。
皆さんは、そこはうまく立ち回り、便宜的に書けばいいと思うでしょうが。職員も地域の人だから、そんなウソは通用しない。筒抜けだ。
富夫君は、成長路線は自分の農業の理念と違うと言って、申請を撤回して帰ってきたという。彼は今もって農業をやめてないから何とか農業機械を買ったのだろう。。
これが全国の水田百姓たちの現状だ。俺が百姓して50年経つけど、50年間では経験したことないようなスピードで家族農、小農が離農していく、やめていく。
あの人は地域のリーダーだったのに・・と、意外な人も、普通の人もやめていく。
4)春、大規模化が作る赤茶けた田んぼ。生き物がいない水田
農水省の推進する「みどりの食糧システム戦略」は、2050年までに有機農業の割合を25%にする。農薬の「使用効果」(使用量?)を5割に、化学肥料を3割削減するとしている。
これは農水省官僚が、ヨーロッパとか近隣諸国に押されながら、やむなく、根拠なく、こういう数字を出さざるを得なかったとしか思えない代物だ。
今のような大規模圃場の広がり、小農の切り捨ての延長線上に有機農業の割合を25%にするなんて不可能だ。かつ化学農薬、化学肥料の3割削減なんてのも無理。論理がめちゃくちゃだ。
大規模化とはケミカル依存農業とセットだ。誰にだってそれは分かる。小農なら有機農業は可能だけど、大規模農業では出来ない。大規模になればなるほどケミカル依存になっていくしかない。それをどんどん水田を拡大し、一方で農薬を1/2以下に減らしていく・・無責任なことを言うな、農水省。遊休農地はたくさんある。だったら見本を見せて欲しい。
田植え直後、一面に広がっている真っ赤な畦畔。除草剤だ。本来、畔とは水田のダム。小さなダムを決壊から護っているのは畔の草。草の根が土をしっかり繋いでダムが破れないようにしている。そこに除草剤を撒くことは、そんな草を根から枯らすこと。雨が降ればボロボロ崩れ、作業のために上を歩けば、ずずっと崩れていく。これでは水田を維持できない。そのことは百姓自身が一番よく知っている。それでも除草剤を撒くのは、畔草を刈れないからだ。労力が無い。
田植えと同時に、除草剤も殺虫剤、殺菌剤、化学肥料も撒く。そして農薬の効力期間が長くなって来た。労力削減のためだ。その結果、田んぼの中の小動物がいなくなった。夕方うるさいぐらいだったカエルは少なくなった。田んぼの虫を食べるツバメもスズメもトンボも少なくいなくなった。沈黙の風景が広がっている。赤茶けた水田、生き物がいない水田。これが大規模化の作る春の風景だ。
5)農業の地域離れ
大規模農業は地域を全く相手にしてない。首都圏、遠くは東南アジアの大都会。置賜の地域なんか相手にしたら、大規模農業なんて成立しない。地域にしてみたらの農村風景は、まさに風景でしかない。自分たちの生活とは関係ない。農産物の地域離れ。
ただでさえ村の過疎化が進むなか、規模拡大によって農業で暮らす人は少なくなっていく。農民であることをやめた人は、村に留まる必要がない。農民の農業離れ、村離れ。総じて家族農業(小農)の消滅。。
6)大規模化の渦中では
大規模化を進めているの渦中の人にインタビューした。
Fさん(小国町)は本業がプロパンのガス屋。従業員からの依頼で田んぼをやり出したら他の従業員も、近所の人もやってくれということで、年間10ヘクタールずつ増えていった。今、60ヘクタール。
山間部で大きな農家と言っても4hを越えなかった地域で、大豆が20ヘクタール、水田が40ヘクタール。農業始めて6年目。さらに増え続けている。
彼の言葉。「小国町で家族専業農業は無理だ。会社勤めプラス二種兼業でどこまでやれるか。やれなくなって俺んところに農地を持ってくる。今、俺の村の農家の平均年齢は75歳を超えている。多くは俺の代で辞めると言っている。新規就農者が水田農業をやるのは無理。1台400万もする機械が必要。同じような価格の田植え機、トラクター、稲刈り機を買いそろえて水田農業なんて採算が合わない。結果的に土建業の方々にお願いするしかない。」
Fさんは、「地域農業を維持する上で、異業種の参入はもう欠くことのできないことだと思うよ。」と言っていた。いまの条件ならば全くそうだ。建設業だってできるかどうか・・。
もう1人の大規模化の渦中の人はBさん。彼は15町歩。彼はコンバインが壊れて、新しいコンバインを見に行ったら1台2000万円。15ヘクタールならそうなるだろう。農協から借金して買った。ところが、下がる一方のコメ価格。ローンが払えない。大規模だから逆にマイナスが大きい。営農資金を貸した農協が機械を持っていったという。彼は農業を続けられなくなって、より大きな農業法人(会社)の職員となった。それで生活がむしろ安定したと喜んでいた。
これが日本を代表する穀倉地帯の置賜地方の中の出来事。雰囲気は分かると思う。
新聞テオリア第134号・2023年11月10日掲載 つづく
連載「おきたまに根をはって」
第6回 農民からの手紙
菅野芳秀(共同代表理事)
寒い日が続いている。
あの日も同じ寒い晩だった。友人の百姓が一升瓶を下げて訪ねてきた。
「熱燗がいいね。」
いい酒があり、いい友がいて、いい時間が流れていく。
やがて彼は懐から封書を取り出し、照れくさそうに私に読んでくれとさしだした。
そこには彼の笑顔と一対の、彼が当時、精魂込めて取り組んでいた世界が書かれてい
た。
いま、その手紙は俺の手元にある。ここに、彼の承諾を得て、その抜粋を掲載す
る。ちょっと長いがぜひお読みいただければありがたい。
2023年1月の今と状況はほぼ同じ。振り返りながら読んでも決して古い感じがしな
い。いまでも、まったく同じことが求められていると思えるのだ。
置賜自給圏
―農民からの手紙(一)・その抜粋
「いま、山形県の南部、置賜〈ルビ=おきたま〉地方(3市5町)で「置賜自給圏」
と名付けられた地域づくりが始まっている。
この自給圏を端的にいえば、「暮らしに必要な資源を、同じ置賜の田畑や森や川に求
めることで生活全般の地域自給を高め、あわせて地域経済の再生や健康増進を促進し
ようとする」ということになろうか。
自給圏の対象は大きく分ければ「食と農」、「エネルギー」、「森と住宅」、「学
び」の4つだ。
「学び」は大事だと思っている。置賜の優れた歴史と伝統を学び、先人の知恵を今
に活かし、ふるさとに生きる誇りを取り戻すこと。これは欠かすことは出来ない。
そして、一般の人と共に、土や農にかかわる機会を増やし、生き甲斐づくり、健康
づくりを通じて医療費削減の世界モデルを構築しようとする。「世界モデル」という
のは大きすぎる話しかもしれないが、私たちの気負いとして受け止めてほしい。さら
に、この事業は、同じ地域の人と人、人と地域のもう一つの出会いを創りだすこと、
地域に根差した新しい文化を創り出すことでもある。」(以下略)
「批判と反対」から「対案」へ
―農民からの手紙(二)・その抜粋
「TPPに象徴されるグローバリゼーションの中で日本の農業の多くは斜陽産業と化
し、農家は果てしなく減少している。数千年の歴史を刻み、多くの人材を世に送って
きた村は高齢化し、その機能すら維持できなくなりつつある。私たちはこの流れに全
力で「NO」を訴えてきたが、それだけではもちろん十分ではない。よしんばTPP
を潰したとしても、右肩下がりの現状はかわらない。求められているのは「反対」を
越えた私たち自身の「対案」であろう。今のようでないもう一つの「農を織り込んだ
暮らしや地域」を築いていくこと。
TPPやグローバル化の中にあっても、なお暮らしていける地域のあり方や人と人
のつながり、仕組みを考えて行く。考えるだけではなく、それらを「対案」として実
際に築いてこうとすることが求められているとおもうのだ。
希望を織り込んだ新しい「対案」を山形、置賜から全国に。この気概をもって置賜
自給圏を創造しようと思う。
ここで肝心なのは、地域(づくり)の操縦桿は永田町、東京などに握られていて、
地域は彼らの幸せづくりの「道具」、「部品」として位置づけられているような現実
があるけれど、操縦桿を地域に取り戻し、その上で各論をみんなの力で創りだそうと
することだ。この立場にお立つことがこの事業の基本だろう。地域の操縦桿と決定権
は地域住民にあるということだ。」(以下略)
対案の前提条件
―農民からの手紙(三)・その抜粋
「その上に立って、グローバリゼーションの道とは違う、もう一つの農業、地域を築
く上での前提条件を考えたい。
【前提1】〝土はいのちのみなもと〟の上に立って
我々は土に依存して生きる。土が汚れれば、そこから育つ作物も汚れ、土の力が弱れ
ば、作物の生命力も弱り、食べる我々の生命力も弱る。我々は土と一体だ。政治や行
政の最大の課題が、人々の健康、すなわちいのちを守ることであるとすれば、そのい
のちを支える土の健康を守ることは第一級の政治課題でなければならない。土といの
ちとの健康な関係を築くことを抜きにし、面積、規模、効率性だけを追うケミカル農
業とその農業政策はすでに過去のものとされなければならない。目先の経済性よりも
いのちの世界を優先させること。土は未来の人たちと共有するいのちの資源。その土
の健康を守ること。これが前提の第一だ。
【前提2】国民(市民)皆農を織り込んだ新しい道
家族農業(小農)か然らずんば企業農業かではなく、たとえば、農を志す都会の若者
たち、農を織り込んだ暮らしを実現したいと願う市民や、自給的な生活を望む人たち
にも広く農地を解放するような仕組み。農民的土地所有(利用)だけでなく、市民的
土地利用を可能とするシステムへの転換。望めばできる市民皆農への道。これを地域
づくりに織り込みながら、新しい農の在り方、生産のあり方、暮らしのあり方、村の
在り方を創造する。「健康」、「福祉」、「医療」、「自給」、「教育」などを織り
込んだ新しい農(土)と人々の関係をもう一つの農地利用の柱として政策化するこ
と。これが前提の第二の条件だ。
【前提3】自給的生活圏の形成を
個人と地域自給が基本。国家の自給はその結果の話であって、けっしてその順番は
逆ではない。我々は国家のパーツではない。
地域農業が地域社会に健康な食材を提供し、地域社会が地域農業の農作物を積極的
に活用することでこれに応える。農地が近くにあることではじめて実現できる豊かさ
を地域の中に取り戻すこと。当然のことながら農作物を地域外に売ることに反対して
いるわけではない。それは「外貨」を獲得するうえで必要なことだ。地域ごと自給自
足のタコツボに入ろうと呼びかけているわけでもない。そうではなく、地域の田畑と
人々の暮らしとをもう一度つなぎなおすことで、本来持っている田舎の豊かさを取り
戻し、それを全国に開いていこうということである。今までのような産業政策一辺倒
ならば、グローバルな市場経済の浸透とともに、地域経済が衰弱し、村の消滅が始
まっていくだろう。村の崩壊は日本農業の再生基盤の崩壊につながり、やがて日本自
身の崩壊へとつながっていくに違いない。
人々の暮らしと地域の中の田畑が有機的、自立的につながること。これが第三の条件
だ。」(以下略)
置賜自給圏推進機構の結成へ
―農民からの手紙(四)・その抜粋
「構想を実現させるにあたって必要なことは、①かつての保守だ、革新だ、あるいは
〇〇党だというような政治的な枠組みにとらわれない生活者・住民の事業としての広
がりをもち、②市民と関係団体、行政が相互に連携する共同事業として育てて行かな
ければならないこと。③単なる同好会のような同じ色合いを持つ者同士が集まって、
何かをしようとしてもこの構想は実現できない。④それぞれ異なった考え、異なった
価値、異なった生き方をしてきたものたちが、相互の違いを認め、尊重しながらつく
り上げられていく連携。この中から「自給圏」が生み出されていくということ。
仲間たちとの議論の中では、この構想の必要性に疑問を投げかけたものはだれもい
なかったが、実現しようという事業の大きさと、「構想案」を囲んで話し合っている
自分たちの非力との落差に話が及ぶたびに、楽天的な笑いが生まれていた。どんな事
業もここから始まる。
(以下略)
余計なひと言
―農民からの手紙(五)・その抜粋
「希望はどこかで我々がやってくるのを待っていてくれるということはない。希望は
だれかが与えてくれるものでもない。それは自分たちで創りだすものであって、それ
以外の希望はけっしてやっては来ない。」(以下略)
これで手紙は終わりだ。微笑みながら静かに酒を飲んでいる彼の顔をみていた。身
体に気を付けてほしい。心からそう思った。
彼は「自給圏を作ろうと集まった人たちにはそれぞれに、それぞれの背景や動機
があり、物語がある。俺はその中の一人でしかない。でも、すばらしい仲間たちの一
員でいることがうれしい。」と繰り返し話していた。
やがて二人はべろべろによっぱらっていった。家の外は厳しい寒さをともなって、
しんしんとふけていく。
2023年の今日。彼らの奮闘にもかかわらず、状況はますます悪くなっている。
「足腰が悪くなってね」
そう言いながらも、久しぶりにやって来た彼は相変わらず笑顔を湛え、楽しそうに
地域の話をする。メゲナイいい奴だよ、まったく。その生き方が気に入っている。そ
れでな、遅ればせながら、今年から俺も彼らの仲間に入ることにしたよ。
もし、あなたが置賜に来てみたいと思ったなら、歓迎するよ。彼もぜひ紹介した
い。一緒に一杯やるべぇ。
連載「おきたまに根をはって」
第5回 コカ・コーラとトカゲ
菅野芳秀(共同代表理事)
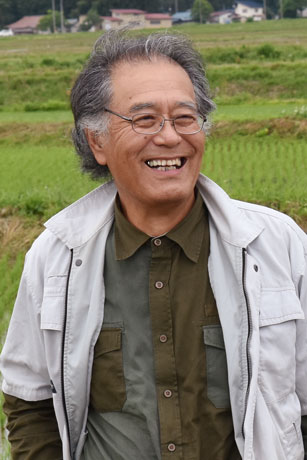
俺は最近とみにコカ・コーラとトカゲを思う。
トカゲをビンの中に入れて飼っていたら、やがて成長しビンから出られなくなって
しまった。そんなトカゲに向かって、お前にはビンを割って出てくる力なぞはあるま
い、そうだろうニッポン・・と寺山修司。コカ・コーラはアメリカ。
戦後80年にもなろうとしているのに・・国を代表する外交政策も、国内政治の舵取
りも、その予算編成も、当然ながら沖縄も、その他の基地問題も、原発も、農業政策
も・・コロナ対策でさえ、コカ・コーラのビンの中。アメリカの言いなりだ。こんな国は世界に例がない。誇りを失ってしまった国、「植民地」ニッポン。
「イイじゃないか、その方が軍事費は掛からないし、安上がりでトクだから」
バカタレ!損得のはなしでない!
この国の自立とそこにすむ人々の尊厳にかかわることだ。
過日、鹿児島の知覧に行って来た。知覧・・特攻隊の出撃基地があったところ。若
くして、特攻で死んでいったたくさんの青年たちの手記に出会うためだ。18歳で、19
歳で、20歳で・・。自分たちの死は避けられないが、そこから未来世代が教訓をくみ
取ってくれるなら、決して俺たちの死は無駄ではないはずだ。そう信じて家族と別
れ、恋人と別れて飛び立って行った多くの青年たち。そんな彼らの、たくさんの手記
に出会えた。
俺は昭和24年生まれ。戦後世代だ。彼らが託した「未来」そのもの。その中に生き
ている。
そして・・・悔しいが、我々もまだにビンの中だ。
彼らに対して恥ずかしくない生き方は当然だが、単なる個人の「生き方」に留まっ
てはならない。
何か特別なことを考えているわけではないが、敗戦の日が近づくにしたがって、毎
年、そんなことを考える。
つづく

連載「おきたまに根をはって」
第4回 車のハンドルを握って町まで買い物に行って来た
菅野芳秀(共同代表理事)

ようやく田植えが終わった。
「大変そうだから手伝いに行くぞぉ」という方もいたが、「チ、チ、チ、チ(と、人差し指をたて左右に振りながら)」そんな訳にはいかない。
都会の人は田植えが一番忙しく、人の助けが最も必要な時期だと「勘違い」している。田植えは大変でないとは言わないけれど、一株一株手で植えていた60年ほど前と違い、田植え機械で行う今は、他の作業と比べて特別に大変だという訳ではなくなっている。
雪解けとともに始まったなが~い農繁期ももうじき一区切り。日々、これまでの成果が緑の早苗の広がりとなって拡大していく。ここまで来ればやれやれ・・だ。そんなところに都会から手伝いに来られたら、それだけでまた一苦労。どうせ手伝いに来てくれるなら農農繁期をはずして来てくれた方がナンボか楽だよな。
ところで今日(6/8)、車のハンドルを握って町まで買い物に行って来た。
ヤッホー!!2年ぶり!
大きな病気の後遺症で、2年ほど前。デスクワークをしていたら、「フッ」と意識が飛んだ。病気のあと、過度なストレスがかかるとそうなることもあるらしい。言われてみたら、母親の介護で夜も昼もなく・・かなりキツイ日々が続いていた。
「お薬も出しているし、もう繰り返すことはないと思いますが・・。」
それでも医師の判断でなんと、2年間の運転停止だと!
車が無ければ不自由極まりない田舎社会。どこに行くにも妻や友人に頼み、連れて行ってもらわなければならなかった。疲れている彼らにビールを2~3本・・などとはとても頼めない。彼らも大変だったと思う。俺は俺で申し訳ないと思っていたし、それだけでなく、常に隣に人がいる窮屈さ。一人になれないことも辛かった。だけどようやく運転免許証が戻って来た。どこへでも行ける。一人の時間もある。ビールも買いに行ける。
その間、様々な「気づき」を得た。あなたがもし、俺と久しぶりに会ったのなら、「あれつ、人が変わったね。」となるかもしれないよ。
しばらく連載を休んでいたのは、家に閉じこもり、ろくなことを考えなかったからだ。田植えは終わったし、運転免許証も戻って来た。あの人にもこの人にも会いに行ける。さあ、これからだ。
つづく
連載「おきたまに根をはって」
第3回 求められているのは『新しい社会主義』佐藤藤三郎さんの話

菅野芳秀(共同代表理事)
佐藤藤三郎さん(農業)、山形県上山市狸森在住。昭和10年生まれの86歳。
藤三郎さんが暮らす地域は奥羽山系の中の山合の村。
果たしてここを車が登れるのかと思えるほどの狭く急な坂道を登って、下って、また登って・・の所にある。
藤三郎さんはその地で田んぼを作り、炭焼きを行い、牛を飼いながら、家族を支え、子どもを育てて来た。
「牛は、10年ほど前に手放したよ。3年前、83歳の時にコメ作りからも引退した。」今は奥さんと二人でわずかに野菜を作り、近くの直売所に運んでいるという。
「田んぼかい?今は雑草が生えたままになっている。田んぼに気の毒でよぉ。田んぼには悪いことをしたなぁと今も思ってるんだ。」
藤三郎さんはペンを持つ百姓として、高畠町の星寛治さん、上山市の木村迪男さん、今は亡き山形市の斉藤太吉さん等と共に山形県で最も有名な農民の一人だ。
農業、農村の立場から現代を捉え、厳しく批評する文化人。
文筆家。それでいて決して偉ぶることなく、いつも親しみやすい笑みを湛えている農民知識人。
尊敬する先輩だ。
過日、藤三郎さんのお話を聞く会をもった。
お話は2時間にも及んだが、いずれも興味深い話だった。
「今は、村祭りも維持できなくなってしまっている。若い人が村に生き残られる。それも堂々と。そんな農村社会を作れたらなぁと思う。」
「兼業化することが村を守ることにつながる。農業を大規模化するのではなく、農+農外収入で村と農業を残す。そんな農村社会がいい。」
日本の農政は長いこと兼業農家を農業の発展を妨げる邪魔な存在、淘汰の対象として来たし、今もその農政は力を失ってはいない。
小農の離農が途切れることなく続いている。
藤三郎さんの話はそれとは真逆の話だ。
俺はその話を聞きながら、ロシアの「ダーチャ」(検索して知ってほしい)を思い浮かべ、置賜自給圏が構想する市民皆農、国民皆農の未来を思った。
「経済をグローバル化するのではなく、小さい農業でいいから、楽しく生きられる社会にしたいものだと思う。」
藤三郎さんの話に引き込まれ、いつしかメモを取ることもできなくなっていたが、最後に力を込めて話した言葉がいつまでも耳に残った。
「求められているのは『新しい社会主義』だと思うよ。」
この一言に、藤三郎さんの歩んで来た足跡、これからも歩み行く方向が凝縮されているように思えた。コロナカ禍のなか、久しぶりに出会えた学びの時間だった。
2022年1月30日記
つづく
連載「おきたまに根をはって」
第2回 帰(かへ)りなんいざ。田園将(まさ)に蕪(あ)れんとす、胡(なん)ぞ帰らざる。

菅野芳秀(共同代表理事)
ご無沙汰しています。
どうにかここまでたどり着きました・・本当にこんな感じで・・岸辺に着いてもなお、ヒーヒーあえいでいます。
「七転八倒百姓記-地域を創るタスキ渡しー」(現代書館)
1977年、百姓として生きようと志を立てて村に帰ったのだけど、「学生運動をやっていた過激派」。こんな包囲網がすでに地域中にあふれていた。さらに百姓1年目から始まった「減反」を拒否したことで、そこに「農協や行政に従わない男」、「村に同調しない男」・・・こんな評判が加わった。生きづらい空気に満ち溢れる。
口笛を吹きながら、七転八倒・・。やがて近隣の農家や、地域の支持を受け、農薬の空中散布を中止に追い込み、そこからレインボープランという循環型まちづくりに漕ぎ出していく。
「自分史」として書くならば、市井の一人でしかない私には始めからその資格はないし、出版する意味もない。
私が百姓のそんな七転八倒記を書けるとしたならば、農民であるかどうかを問わず、同じような孤軍奮闘の日々を送っている友人たちに、何らかの連帯のメッセージを伴ったものでなければならず、また同時に私の体験が少しでもその方々のお役に立てること。これがあって始めてその資格ができ、出版する意味もあるだろうと思ってきた。果たしてそのような一冊になれたかどうかは、今でもまだ心もとない。(本文あとがきより)
出版社よりありがたい内容紹介をいただきました。
内容紹介(出版社より)
著者は、長年にわたり農民として可能性に満ちた地域を守り、次世代に手渡すために、減反拒否、村ぐるみの減農薬運動、生ゴミと健康な作物が地域を循環するまちづくり等々に取り組んできた。グローバリズムを背景に小さな農家が切り捨てられていく危機に直面しながら、地域自給圏の創出、都市と農村の豊かな連携に今も力を注ぐ。アジア各国の農民リーダーと共に変革を生み出し、互いに学び合う関係を築いてきた著者のバイタリティーが、リズム感ある筆致から溢れ出す。
この本を、年齢を問わず同じ時代を「七転八倒」しながら生きている、まだ見ぬ仲間たちに。そして同じ世代の仲間たちにも心からの連帯の気持ちを込めて送りたい。特に同世代には「すでに一つの山を越えたし、七〇歳だから」という人もいるが、自分の生き方を決めるのは志と情熱であって、自然年齢ではない。そんなものに左右されてたまるもんか。対象は、よりひどくなって我らの前にその醜態をさらしている。
「帰(かへ)りなんいざ。田園将(まさ)に蕪(あ)れんとす、胡(なん)ぞ帰らざる。」である。ともに参りましょうぞ!
菅野芳秀 山形県長井市寺泉1483
携 帯:090-4043-1315
メール:narube-tane@silk.ocn.ne.jp
2021年10月15日金曜日
置賜自給圏推進機構の代表理事の一人 菅野芳秀共同代表 が長い沈黙を破ってついに執筆活動に入った。その第一弾を置賜自給圏推進機構に連載を開始。タイトルは「おきたまに根をはって」。農家として思想家として菅野節がさく裂するかもしれない注目の第1回。
連載「おきたまに根をはって」
第1回 地域づくりに必要なこと

菅野芳秀(共同代表理事)
個人的にちょっとした出来事があって、自給圏の活動を休まざるを得ない期間があった。その間、あれやこれやを振り返りながら色んな事を考えていた。それらの多くはとても文章に出来る代物ではないが、今回、置賜自給圏の事務局から短文の依頼を戴いたことを機会に、あまり気張らずに考えていたことのひとつ、ふたつを書いてみようと思う。
今回は最初という事もあって、少し背伸びした硬い文章となっているが、その辺は人物の小ささの現われとしてお見逃し戴ければありがたい。
地域づくりに必要なことは、出来るだけ大きな視点に立って遠くを見とおし、地域の可能性を考えて見るということ。時代は大きな転換期を迎えている。どんな転換期か。いささか言い古されてはいるが、本筋は変わらない。工業系が主導した生産効率を何よりも優先した資源収奪型社会から、社会が持続的であることを最優先課題とする生命系が主導する地域循環型社会へ。
この文明史的とも言える大転換期の中にあって、その転換に成功するかしないかの中に、我々が生存し続けることが出来るか否かがかかっている。地域づくりもまたこの大きな文脈を反映したものでなければならない。
私は農民だ。よって、農民の立場からこの大きな転換期に参加しようと思って来た。つまり大きな世界観のなかに農業を位置付け、農を基礎とする循環型社会を作り出すこと。そんな視点に立った地域政策、市民の政策が必要だ。1980年代後半ぐらいからずっと言われている「地球的に考え、地域的に活動する」と言うことである。
これでは駄目だといくら繰り返しても社会は変わらない。難局には対案(地域政策)をもって参加する。その具体的展開を農村の中から考えていこうと思って来た。
さて、転換期とは理想を語る時代である。別な言い方をすれば、大きな夢を語り、それを行動に移す時代ということもできる。理想と夢がなければ取り組む意味がない。理想と夢があってもそれを実行に移さなければ何にもならない。希望に決意を込める。理想を形にすること。転換期とはそのような時代の事を言う。自給圏の出発点もここにあろう。
その視点を持って足元を見わたして見る。そこには我々が棲む大好きな置賜盆地が広がっている。中に分け入れば、もちろんそこには我々が誇る様々な良さがあるが、ここをこうしたいという改善点もない訳ではない。でも、その欠点を指摘する前に大切なのは、まず今そこにある地域を丸ごと肯定するということ。ここまで地域を伝えて来てくれた先人の思いと努力に感謝し、その思いを受け継ごうとするところから地域づくりはスタートする。ここが基本であり、地域づくりの出発点もここにあると思っている。
そこで・・あっ、紙面が尽きた。この続きは次回で。
2021年9月3日金曜日
よろしければご感想をお寄せください。
「オーガニックフェスタ米沢」出店募集について
置賜自給圏ニュース 2017年9月21日木曜日
置賜自給圏推進機構の小関恭弘理事から「オーガニックフェスタ米沢」出店募集のお知らせがきています。
小関理事は「米沢地域有機農業推進協議会」の会長です。
今回で4回目を迎える「オーガニックフェスタ米沢」にぜひあなたの生産品を出店してみませんか。
内容は次のとおりです。
有機農業に関する情報の発信と食の安心・安全に関心のある消費者との交流を図るため、4回目となる標記イベントを下記のとおり開催することになりました。
つきましては、出店募集について下記のとおり御案内申し上げますので、この機会にぜひ御出店いただき、PRや交流の場として御活用ください。
記
1 日 時 平成29年11月12日(日) 9:30~14:00
2 会 場 米沢総合卸売センター P-PAL
(米沢市中田町760)
3 申込締切 平成29年9月27日(水)
*チラシ掲載の都合上、期限厳守でお願いいたします。
4 そ の 他
(1) 多数の申込みがあった場合、出店いただけない場合があります。
その際、イベント趣旨の都合上、有機栽培農産物やオーガニック商品を扱う店舗を優先的に受付けさせていただきます。
(2) イベント当日、各出店者様より商品を提供していただき、来場者を対象とした抽選会を企画しています。
農産物や各店で使える商品券などなんでも結構ですので、御提供賜りますようお願い申し上げます。
御提供いただける場合は、申込書に記載願います。
(3) その他、詳細については別紙出店募集要項を御覧ください。
米沢地域有機農業推進協議会
会長 小関 恭弘
オーガニックフェスタ米沢 出店者募集要項
■開催概要
期日 2017年11月12日(日)9:30 ~ 14:00
会場 米沢総合卸売センター P‐PAL(〒992-0011 米沢市中田町760)
主催 米沢地域有機農業推進協議会
後援 米沢市、山形県有機農業者協議会
内容 地元有機農産物や特別栽培農産物、関連する加工品などの販売、 その他催し物。有機農業や有機農産物普及のためのPR など
予定来場者数 400名
出店者数 20程度
■出店要項
出店要件
①オーガニックフェスタ米沢の趣旨に合致していること(主催の判断による)。
②販売商品に「有機栽培」や「特別栽培」など消費者が一目でわかるよう包装や店頭掲示で表示すること。
③慣行栽培に由来する農産物や加工品の展示・販売は原則禁止させていただきます。有機的生産加工が困難で、配慮が必要な商品を出品希望の場合は、事前に米沢地域有機農業推進協議会の確認をお願いします。
ブース概要 大きさ:2m×2m 付属品:長テーブル(180cm×45cm)2台、椅子2脚
料金 出店料:3,000円/1ブース
電気使用料(申請した場合):2,000円/1口
設備 電気:申込書にて申請ください。
水道:会場2階の設備を使用いただきます。
ガス:なし。使用したい場合は各自でカセットコンロを準備願います。
商品搬入 当日午前8時30分~9時10分 搬入口(北側・南側 2か所)から搬入
申込方法 申込書に必要事項を記入し、FAXまたは郵送にて下記担当までお申し込みください。
申込期限 平成29年9月27日(水)
売上金 全額各店舗の収入
各種申請 飲食物の販売は「臨時営業許可」が必要です。各自保健所に申請してください。
(無料提供(ふるまいや試食)の場合、許可は不要です。)
■申込先
米沢地域有機農業推進協議会 事務局(米沢市農林課内)
〒992-8501 米沢市金池5丁目2番25号
電話:0238-22-5111(内線5008) FAX:0238-24-4541
以上です。
【江口忠博】レインボープラン…「循環型社会」への挑戦(2015年3月20日)
【野村浩志】恋よ来い!「ホワイトデー」は木造駅舎で「恋&鯉」交流会(モニター企画第2弾)(2015年3月19日)
【菊地富夫】生産者からの手紙(2015年2月17日)
【野村浩志】〜おきたまの地酒 · 美味な食材を楽しむ農家&酒蔵列車~おきたま五蔵会&置賜自給圏推進機構列車運行(2015年2月16日)
【菅野芳秀】置賜自給圏ー農の現状から(2015年2月12日)
【菅野芳秀】友人の手紙 (2015年1月11日)
【塚田弘一】塚田農園・歌丸燦工房(うたまるさんこうぼう)のお話し。(2014年12月21日)
(*)置賜自給圏は今、何をしているのか、何を目指しているのか、各理事の視点で語ってもらいます。
一般社団法人 置賜自給圏推進機構設立総会 ご案内(*終了しました)

本機構の趣旨に賛同される皆様のご参加をお待ち申し上げます。
1)日時:2014年8月2日(土)午前10時 〜 午後12時30分
2)場所:米沢市「置賜総合文化センター」1Fホール
米沢市金池3丁目1−14 電話:0238-21-6111
3)1部 設立総会 2部 記念講演 講師:島根県 海士町長 山内道雄氏
(過疎の海士町をよみがえらせた成功事例をお話いただきます)
4)参加費:無料
5)連絡先(参加ご希望の方はFAXかメールで事前のご連絡をお願いします)
一般社団法人 置賜自給圏推進機構 設立準備委員会
〒992-0031 山形県米沢市大町4丁目5番48号 マツヤ書店ビル3F
電話:0238-33-9355 FAX:0238-33-9354
以上
設立総会のご案内(参加無料)(*終了しています)

地域資源を基礎とした「置賜自給圏構想を考える会」
設立総会のご案内
1)日時 平成26年4月12日(土) 13:00~15:30
2)場所 伝國の杜 「大会議室」(2F)
山形県米沢市丸の内1-2-1
電話 0238-26-2666
3)内容
◯設立総会
◯記念講演 「新しいローカリズム-置賜自給圏構想への期待-」 (仮題)
講師 山形大学 人文学部長 北川忠明 氏
4)その他 ご出欠につきましては、4月11日(金)までお知らせ願います。
*)また、当日の参加費は無料ですが、カンパ大歓迎です。
*)託児あります。(お子様1人につき300円。定員15名まで。事前申込必要です。お子様の年齢をご連絡下さい。託児の申込締め切りは4月9日(水)まで)
(託児は定員に達しましたので、締め切らせていただきます)
5)問い合わせ先
地域資源を基礎とした「置賜自給圏構想を考える会」仮事務局
〒990-0021 米沢市花沢町2695‐4(今井医院 西隣)
グループホーム結いのき内
電話 090-3122-5530(井上)
Fax 0238-37-0961
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
拝啓 寒さの中にも春の足音が聞こえてくる季節になりました。皆様にはご健勝でご活躍のこととお喜び申し上げます。
さて近年、国ごとの規制や制度の枠組みを越え、世界を一つの市場にして規模と価格とコストの果てしない競争を強いていく、こんな動きが勢いを増し、国内の零細企業、家族農業、地域経済の先細りが進んでいます。
この状況を打開するために、置賜を一つの「自給圏」ととらえ、圏外への依存度を減らし、圏内にある豊富な地域資源を利用、代替していくことによって、地域に産業を興し、雇用を生み、富の流出を防ぎ、地域経済の好循環をもたらすという、新たな視点に立った地域づくりを検討しようという声が大きくなってきています。
そこで、圏内有志が集い、置賜の農業やエネルギー資源と地域との関わりについて、人々の暮らしをつなぐ新しい地域のあり方を考える“地域資源を基礎とした「置賜自給圏構想を考える会」”設立に向けた準備を重ね、「設立趣意書」(案)を作成いたしました。
基礎的生活資源の自立、自給こそ地域づくりの根本とするこの「置賜自給圏」構想は、かつて米沢藩の名君と讃えられた上杉鷹山公の地域づくりと通い合うところがあるように思われます。
つきましては、「置賜自給圏構想を考える会」の設立総会を、多くの圏内有志のご参加を得て、開催したいと存じますので、ご趣旨にご賛同いただき、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
敬 具
一般社団法人 置賜自給圏推進機構 〒992-0031山形県米沢市通町六丁目16番57号 生活クラブやまがた2F TEL:0238-33-9355 FAX:0238-33-9354
